結婚式の二次会は、新郎新婦とゲストが自由に交流し、笑顔があふれる時間。披露宴の緊張感から解放されて、ゲームや歓談で盛り上がるカジュアルな場です。
でも、その成功の裏には「幹事」の存在があります。会場探し、進行管理、景品手配、当日の司会や受付…とにかくやることが多い!
そこで重要なのが「幹事は何人で担当するのがベストか?」という問題です。1人で仕切るのか、複数で分担するのかによって、準備の負担や当日の運営が大きく変わります。
この記事では、幹事の適正人数とその理由、人数ごとのメリット・デメリット、さらに決め方のポイントまで詳しく解説します。これから幹事を依頼する新郎新婦や、幹事を引き受ける予定の方はぜひ参考にしてください。
幹事の主な役割と必要な作業量
まずは幹事の仕事内容をおさらいしましょう。人数を決める際には、この作業量をイメージすることが大切です。
- 会場探し・予約
- ゲームや余興の企画
- 景品・備品の手配
- 招待状や案内の作成・送付
- 当日の受付・司会・進行管理
- 会費の集金と精算
これらを1人で全部やるのはかなり大変。特に招待人数が50名を超える場合や、ゲーム・景品が充実している場合は、複数人での運営がおすすめです。
幹事人数別のメリット・デメリット
幹事1人
メリット
- 意思決定が早く、打ち合わせがスムーズ
- 責任の所在が明確
- 調整役が1人なので混乱しにくい
デメリット
- 負担が集中し、準備〜当日まで忙しすぎる
- 体調不良や急用に弱い
- アイデアが偏りやすい
こんな場合におすすめ:小規模(20〜30名程度)、カジュアルな飲み会形式、ゲームや余興なし
幹事2人
メリット
- 作業を分担できる(例:司会役と受付役)
- お互いにフォロー可能
- 負担が軽く、準備も楽になる
デメリット
- 意見が合わないと決定が遅れる
- 片方に負担が偏る可能性
おすすめの役割分担例:
- 幹事A:会場・進行管理、ゲーム企画
- 幹事B:景品手配、招待管理、会計
幹事3〜4人
メリット
- 役割を細かく分けられる(司会、受付、会計、ゲーム進行など)
- 当日も余裕があり、ゲストとの交流もしやすい
- 1人欠けてもカバーしやすい
デメリット
- 打ち合わせの日程調整が大変
- 意見が割れやすく、まとめ役が必要
理想の人数帯:中規模(40〜70名)、余興やゲームあり、景品も多めの場合
幹事5人以上
メリット
- 大人数の二次会でも余裕をもって運営できる
- 当日は持ち場を固定しやすく、スムーズ
デメリット
- 連絡調整の手間が大きい
- 責任感が薄れやすい(「誰かがやるだろう」状態)
おすすめケース:大型会場、参加人数100名超、余興複数あり
幹事人数の決め方のポイント
- 参加人数から逆算する
目安として、20〜30名で1〜2人、40〜70名で3〜4人、100名以上で5人以上が理想。 - 役割の数で決める
司会、受付、会計、景品係、進行補佐などの役割を数えて、それぞれに担当を割り当てる。 - 信頼関係で選ぶ
人数が多くても信頼できないメンバーだと逆効果。信頼度重視で選びましょう。
実例:60名規模の二次会での幹事編成
- 幹事A(司会・進行)
- 幹事B(景品・ゲーム進行)
- 幹事C(受付・会計)
- 幹事D(写真・動画撮影担当)
この形なら当日も慌ただしくならず、ゲストとの交流も楽しめます。
トラブルを防ぐための工夫
- 幹事全員でLINEグループを作り、進捗を共有
- 役割分担は文書化して配布
- 急な欠席に備えて予備担当を決めておく
まとめ
幹事の適正人数は、参加人数・会の規模・やることの多さによって変わります。少なすぎれば負担が大きく、多すぎれば調整が大変。
目安を押さえて、信頼できるメンバーでバランスよく構成するのが、楽しくスムーズな二次会の秘訣です。
※おすすめの二次会代行業者は記事下の一覧をご覧ください。
編集部おすすめの二次会幹事代行会社のセクション
最後に、編集部のおすすめ二次会代行をご紹介いたします!
記事の最後には二次会代行別の特徴をまとめた比較表を掲載しています!一気に比較してみたいという方は以下のボタンから比較表を見てみましょう!





.png)
.jpg)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)



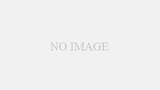














コメント