友人同士の集まりや同窓会、会社の送別会など、さまざまな場面で開かれる「二次会」。
楽しい時間を作るには、お店選びや進行管理、会計などを仕切ってくれる「幹事」の存在が欠かせません。
ただ、悩みやすいのが「幹事は何人でやるのがちょうどいいの?」という点です。
人数が少なすぎると負担が集中し、多すぎると連絡調整が面倒になる…。
この記事では、二次会の規模や目的に合わせた幹事の適正人数、人数ごとのメリット・デメリット、役割分担のコツを解説します。
これから幹事を決める人も、すでに引き受けている人も、よりスムーズに進めるヒントになりますよ。
幹事の主な役割とタスク量を把握しよう
幹事の仕事は「お店の予約」だけではありません。
規模によっては、次のようなタスクが発生します。
- 会場探し・予約
- 出欠確認・招待連絡
- 当日の進行管理(乾杯、ゲーム、締めの挨拶)
- 会計・集金・精算
- 写真や動画の記録
- 景品や小物の準備
幹事人数を決めるときは、この作業量を分担できるかどうかがポイントです。
幹事人数別の特徴
幹事1人
メリット
- 意思決定が早く、話がまとまりやすい
- 調整役が一人なので責任が明確
デメリット
- 負担が大きく、準備から当日まで忙しい
- 急な用事で来られなくなると代わりがいない
おすすめケース
- 参加人数が10〜20名程度
- シンプルな飲み会形式
幹事2人
メリット
- 作業を分担できて負担軽減
- お互いにフォローできる
デメリット
- 意見のすり合わせが必要
- 得意・不得意で片方に負担が偏ることも
役割分担例
- 幹事A:会場・進行
- 幹事B:会計・景品管理
幹事3〜4人
メリット
- 受付・司会・会計・進行補佐など役割を細かく分けられる
- 当日余裕を持って動ける
デメリット
- 打ち合わせの日程調整が難しい
- 役割を決めないと責任があいまいになる
おすすめケース
- 参加人数30〜60名
- ゲームや余興が多め
幹事5人以上
メリット
- 大規模でも対応可能
- 持ち場を明確にすれば非常にスムーズ
デメリット
- 調整や連絡が煩雑になる
- 「誰かがやるだろう」と責任感が薄れがち
おすすめケース
- 参加人数80名以上
- 複数の進行イベントがある
幹事人数を決めるコツ
- 参加人数に応じて割り出す
20名ごとに1人を目安に設定すると無理がない。 - イベント内容を考慮する
余興やゲームが多ければ多めに配置。 - 信頼できる人を選ぶ
数より質が大切。動ける人を確保しましょう。
まとめ
幹事の人数は、二次会の規模や内容で大きく変わります。
小規模なら1〜2人、大規模なら3人以上が目安。
大事なのは「負担を分散できる人数」と「連絡がスムーズなメンバー」であることです。
これを押さえれば、当日も安心して楽しめます。
※おすすめの二次会代行業者は記事下の一覧をご覧ください。
編集部おすすめの二次会幹事代行会社のセクション
最後に、編集部のおすすめ二次会代行をご紹介いたします!
記事の最後には二次会代行別の特徴をまとめた比較表を掲載しています!一気に比較してみたいという方は以下のボタンから比較表を見てみましょう!





.png)
.jpg)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)



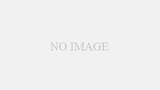














コメント